手動式の万能みじん切り器「ぶんぶんチョッパー」が、実はとろろ作りにも大活躍!
通常はすりおろし器を使って時間がかかる長芋のとろろが、ぶんぶんチョッパーなら秒で完成してしまうと話題に。本記事では、
-
ぶんぶんチョッパーでとろろを作る手順
-
注意点やコツ(ねばり気や水加減の調整など)
-
とろろを使った簡単&美味しいアレンジレシピ5選
(例:とろろそば、とろろご飯、和風グラタンなど)
を分かりやすく紹介します。
ぶんぶんチョッパーの意外な活用法を知りたい人や、とろろ料理のレパートリーを増やしたい人にぴったりの記事です!
ぶんぶんチョッパーってなに?基本を知ろう
手動の秘密:電気いらずの便利さ
ぶんぶんチョッパーは、手で引っ張るだけで中に入れた食材をみじん切りにできる便利グッズです。電気がいらないので、キッチンのコンセントを気にせずにどこでも使えるのが特徴。仕組みはとてもシンプルで、ふたについている紐を引っ張ると中の刃が回転し、食材をどんどん細かくしてくれるんです。これだけで玉ねぎのみじん切りやにんじんの細切りなどが、ほんの数秒でできてしまいます。
さらに、火を使わないからお子さんでも安心して使えるのも魅力の一つ。キャンプなどのアウトドアでも大活躍しますし、朝の忙しい時間でも「ぶんぶん」するだけで、すぐに調理の下ごしらえが完了するんです。とくに料理が苦手な人や、包丁を使うのが怖いという人にもぴったり。楽しく、そして簡単に料理のハードルが下がるアイテムです。
分解してみた:構造と仕組みをチェック
ぶんぶんチョッパーの構造は、とてもシンプルです。本体は大きく分けて3つのパーツでできています。「容器」「刃のパーツ」「ふた」の3つです。この中で最も重要なのが、ふたに付いているヒモ。これを引っ張ることで、ふたの内側にあるギアが回転し、容器内の刃がぐるぐると回ります。つまり、ヒモを引く力だけで刃が高速で回転してくれるのです。
この仕組みのおかげで、力の弱い人でも簡単に食材を細かくすることができます。また、刃の数も重要で、2枚刃や3枚刃などモデルによって異なります。刃が多いほど一度に切れる量が増え、より細かくなります。ただし、あまりに長く引きすぎると食材がペースト状になってしまうので注意も必要です。分解して洗えるのもポイントで、衛生的にも安心です。
使える食材・使えない食材とは?
ぶんぶんチョッパーはさまざまな食材に使えますが、すべてが万能というわけではありません。使える食材としては、玉ねぎ、にんじん、キャベツ、ピーマン、そして今回の主役「長芋」など、ある程度やわらかい野菜が中心です。果物ならバナナやキウイなど、繊維が少なくて水分が多いものが向いています。
一方で、使いにくい食材もあります。たとえば、かたい根菜のごぼうや、繊維が強すぎるセロリなどはうまく切れず、刃を痛めてしまうことも。また、魚や肉などのたんぱく質系も粘り気があるため、詰まりの原因になります。ぶんぶんチョッパーはあくまで「みじん切り」や「とろろ」などを作るのに特化しているため、向き不向きを理解して使うことが大切です。
とろろを作るならこれ!ぶんぶんチョッパー活用術
長芋はどう切る?とろろ作りのコツ
とろろを作るには、まず長芋を適切な大きさに切ることが大切です。ぶんぶんチョッパーを使う場合、あらかじめ皮をむいた長芋を3~4cmの輪切りにしてから、さらに縦半分に切ると使いやすくなります。大きすぎると刃に絡まりやすく、逆に小さすぎるとうまく回転しないこともあるため、ちょうどよい大きさが必要です。
長芋は粘りがあるので、手で直接触るとすべりやすくて危険です。そんなときはビニール手袋を使ったり、濡らしたふきんで包んでから持つと安全です。切った長芋を容器に入れたら、ふたをしっかり閉めて準備完了。あとはヒモを何度か引くだけで、とろろの完成が見えてきます。
ぶんぶんチョッパーは特に長芋との相性が良く、包丁やすりおろし器よりも手早くなめらかなとろろが作れます。さらに手がかゆくなりにくいというメリットもありますよ。
なめらかにするための回数とコツ
とろろをぶんぶんチョッパーで作るとき、なめらかさを決めるのは「引く回数」です。だいたい20〜30回ほど引くと、ほどよいとろみと滑らかさのあるとろろになります。最初はゴロゴロした状態でも、引くたびにどんどん細かくなっていくので、様子を見ながら引く回数を調整しましょう。
また、途中でふたを開けて、ゴムベラなどで中の長芋を軽く混ぜるのもコツのひとつです。これで刃の回転がスムーズになり、均一にすりおろされます。もし途中で粘りが強すぎて動きが悪くなったら、少量の水やだし汁を加えるといいでしょう。無理に引き続けると、ヒモが壊れる原因になるので注意です。
できあがったとろろは、すぐに食べてもよし、冷蔵庫で保存しても味が落ちにくいのが特徴です。作りたてのふわっとした食感を楽しみたいなら、できるだけ早く食べるのがおすすめです。
洗い物を減らす使い方
ぶんぶんチョッパーを使うと、洗い物がとても少なくて済むのも魅力の一つです。包丁やすり鉢を使わないので、汚れるのは基本的に「容器」「刃」「ふた」の3つだけ。しかも、これらはすべて分解して水洗いできるので、とてもラクです。
さらに洗い物を減らしたいなら、ぶんぶんチョッパーの容器をそのまま「ボウル代わり」に使うのがおすすめです。とろろを作ったあとに調味料を加えて混ぜたり、そのまま冷蔵庫に入れて保存したりと、一つの容器で完結できます。
ポイントは、使用後すぐに洗うこと。とろろは乾くとこびりつきやすいので、ぬるま湯を使ってサッと洗うだけでキレイになります。刃の部分だけは少し注意して、スポンジでやさしく洗いましょう。使いやすくて片付けも簡単、だからこそ毎日使いたくなるんですね。
ChatGPT:
とろろアレンジレシピ3選!毎日食べても飽きない
ごはんにかけて!とろろ丼の黄金比
とろろといえば、やっぱりごはんにかける「とろろ丼」が定番です。でも、ただかけるだけじゃもったいない!ちょっとした工夫で、驚くほど美味しくなるんです。とろろ丼の美味しさを引き出す黄金比は、「とろろ3:だし1」の割合。とろろに対して、少しだけだし汁を加えることで、風味がグッと増してごはんとの一体感が出ます。
だしは、かつおや昆布の和風だしがベスト。市販のめんつゆを薄めて使ってもOKです。さらに味に深みを加えたいなら、しょうゆをほんの少しだけ垂らしてみましょう。お好みで卵黄をのせると、さらにまろやかになって贅沢な味わいに。青のりや刻みのりをふりかければ、香りと見た目のアクセントになります。
朝食にもぴったりで、胃にやさしく、栄養もたっぷり。食欲のない日でもつるんと食べられて、体にやさしい一品です。
そばにも合う!だし香るとろろつゆ
とろろはごはんだけでなく、そばと合わせても絶品。冷たいそばに、だしととろろを合わせたつゆをかければ、暑い日にもぴったりの「とろろそば」が完成します。作り方はとっても簡単。ぶんぶんチョッパーで作ったとろろに、めんつゆを3〜4倍に薄めたものを加えてよく混ぜるだけ。
ポイントは、とろろを混ぜすぎないこと。少し粘りが残るくらいの方が、そばに絡みやすくて美味しいです。また、わさびや刻みねぎ、大葉などの薬味を加えると、風味がグンとアップ。とくに夏場は冷たいそばと一緒に食べると、さっぱりしていて食欲がないときにもぴったりです。
さらに、温かいそばにも応用できます。温かいだしにとろろを溶かし入れれば、ふんわりとしたとろろがとろけて、体がポカポカに。季節に合わせて楽しめる万能アレンジです。
洋風アレンジ!とろろグラタン
とろろ=和食、と思っていませんか?実はとろろは洋風にもアレンジできるんです。おすすめなのが「とろろグラタン」。すりおろした長芋に少量の牛乳とコンソメを加えて、具材と一緒にオーブンで焼くだけ。ふわっとした食感と、まろやかな味わいがクセになる一品です。
作り方は簡単。ぶんぶんチョッパーでとろろを作ったら、そこに牛乳(とろろの半量程度)とコンソメ少々、塩こしょうを加えてよく混ぜます。具材には、茹でたブロッコリーやベーコン、きのこ類がおすすめ。耐熱皿に具材を入れ、とろろ液を流し込み、チーズをのせてオーブンで焼くだけです。
焼き上がると、表面はこんがり、中はふわふわ。和と洋がミックスされた新感覚のグラタンになります。子どもにも大人気で、いつものおかずにちょっと変化を加えたいときにもぴったりです。
お手入れ簡単!ぶんぶんチョッパーを長く使うために
使用後すぐがカギ!洗い方の基本
ぶんぶんチョッパーを長く使うためには、使ったあとのお手入れがとても大切です。とくにとろろのような粘り気のある食材を扱った後は、すぐに洗うのがポイント。時間がたつととろろが乾いてこびりついてしまい、落とすのが大変になります。
洗うときはまず、刃の部分に注意。とても鋭いため、直接手で触らずにスポンジやブラシを使いましょう。ぬるま湯を使うと粘りも落ちやすくなります。ふたのヒモ部分は水が入りやすいので、洗ったあとはしっかりと水を切って乾かすのがコツ。ときどきふたを逆さにして、自然乾燥させるのもおすすめです。
本体の容器と刃は食洗機対応のモデルもありますが、説明書を確認してから使いましょう。手洗いなら中性洗剤で優しく洗えば、いつでも清潔に保てます。毎日使う道具だからこそ、きれいに保つことが長持ちの秘訣です。
部品の寿命と買い替え目安
ぶんぶんチョッパーは丈夫な作りですが、使い続けるとどうしても摩耗や劣化は避けられません。特に刃の部分は、頻繁に使うほど切れ味が落ちてきます。刃の切れ味が悪くなったと感じたら、それは買い替えのサインかもしれません。
また、ふたのヒモ部分も劣化しやすいパーツのひとつです。引いたときに戻りが悪くなったり、引っかかるような感覚があれば注意。ヒモが切れる前に交換できれば安心です。メーカーによっては部品だけの購入が可能な場合もあるので、公式サイトなどをチェックしてみると良いでしょう。
使い方や頻度にもよりますが、平均的には1〜2年ほどがパーツの交換目安。異音がする、回転がスムーズじゃないなど、普段と違うと感じたときは点検するのがおすすめです。適切なタイミングでの買い替えが、快適な使用につながります。
カビを防ぐ!保管方法のコツ
ぶんぶんチョッパーの保管で気をつけたいのが「湿気」。洗ったあとにしっかり乾かさないまま片付けてしまうと、カビやにおいの原因になります。特にふたの内部や刃の根元など、水がたまりやすい部分は要注意です。
保管のコツは、しっかり乾かしてから収納すること。できればすべてのパーツを分解し、風通しの良い場所で乾燥させましょう。ふたは逆さにして、ヒモの部分にも空気が通るようにすると安心です。乾いたら清潔な布巾やキッチンペーパーで軽く拭いておくと、さらに効果的です。
また、使用しないときは密閉容器やビニール袋などに入れず、通気性のある場所にしまうのが理想。湿度の高い梅雨の時期などは、除湿剤を近くに置くとカビ対策になります。ちょっとした工夫で、いつでも清潔に保てるんです。
みんなの口コミとおすすめポイント
SNSで話題の使い方を紹介
ぶんぶんチョッパーはSNSでも話題になっていて、「こんな使い方があったのか!」というアイデアがたくさん投稿されています。特に人気なのは、時短レシピや離乳食づくりのテクニック。細かく刻むだけでなく、ペースト状にもできるので、赤ちゃんのごはん作りにもぴったりなんです。
また、氷を入れてシャーベットを作るというアイデアも人気。氷と果物を一緒に入れてぶんぶんするだけで、即席スムージーが完成します。夏のおやつに最適です。他にも、にんにくやしょうがのすりおろしにも便利との声があり、小分けして冷凍保存すれば調理の時短にもなります。
TikTokやInstagramでは、アレンジレシピや実演動画が多く、見ているだけで参考になります。「#ぶんぶんチョッパー」で検索して、いろんな使い方を試してみるのも楽しいですよ。
リアルな口コミ:良い点・悪い点
実際に使っている人たちの声には、参考になるものがたくさんあります。良い点として多く挙がるのが、「簡単に使えて時短になる」「電気を使わないからエコ」「子どもと一緒に使える」ということ。特に子育て中の家庭や、忙しい朝に使いたい人にとっては大助かりのアイテムです。
一方、悪い点としては「ヒモが切れやすい」「大量に作るのには向いていない」という声も見られます。たしかに、少量の食材を処理するには便利ですが、大量にやると何度もヒモを引かなくてはならず、少し大変です。また、長く使っていると刃の切れ味が落ちてくるという指摘もあります。
でも、総合的には「買ってよかった」という意見が圧倒的に多く、使い方を工夫すれば長く愛用できるアイテムであることは間違いありません。
他のスライサーと何が違う?
スライサーやフードプロセッサーと比べて、ぶんぶんチョッパーの最大の違いは「手軽さ」にあります。電気式のフードプロセッサーはパワフルですが、準備や後片付けが面倒。一方ぶんぶんチョッパーは、取り出してすぐに使えて、終わったらサッと洗えるというお手軽さが魅力です。
また、コンパクトで収納場所にも困らず、キッチンのちょっとしたスペースに置いておけます。音も静かなので、早朝や深夜でも周囲に気を使わずに使えるのもポイント。手動だからこそ、自分のペースで「みじん切り」や「すりおろし」ができるのも、他にはない魅力です。
もちろん、大量に作りたいときには電動の方が便利なこともありますが、日常的に少しだけ使いたい人にとっては、ぶんぶんチョッパーのほうが断然便利。自分のライフスタイルに合わせて使い分けるのがおすすめです。
まとめ
ぶんぶんチョッパーは、みじん切りだけでなくとろろ作りにも使える万能アイテムです。手間のかかる長芋のすりおろしが、手軽に数秒でできるのは驚きですよね。
今回紹介したアレンジレシピ5選を活用すれば、とろろをもっと日常の食卓に取り入れやすくなります。とろろご飯やそばだけでなく、グラタンやお好み焼き風などバリエーション豊かなメニューが楽しめるのも魅力。
「ぶんぶんチョッパー、みじん切りだけじゃもったいない!」
ぜひこの記事を参考に、とろろの新しい楽しみ方を試してみてくださいね。

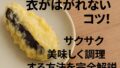

コメント